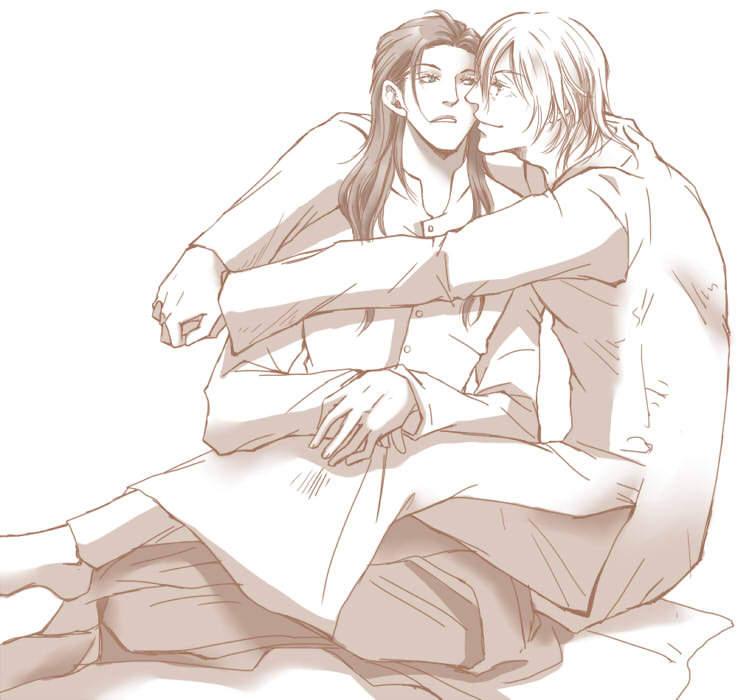聖界に招かれ、一通りあちこちにたらい回しにされ、慎ましやかな非難の目と苦情の挙句に配された討伐隊で出会ったルベウスは、デキウスの目から見てもややズレていた。
品行方正で厳格、かつ監督的な役割のフィディウスからの評価も高く、それゆえにデキウスのフォローをするようにと任された男だった。
決して無愛想ではないが表情豊かとはとても言えず、何に対しても淡々とした反応と態度しか返さないが、だからといって潔癖で融通の利かない聖族の典型でもなく、討伐ではむしろデキウスですら驚かされるような激情型の殺戮を繰り広げる。
さらには神々からの寵愛が厚いのを良いことに、自分の美的感覚を優先し、見つかれば懲罰を食らうような穢れたものを浄化してこっそり持ち込んでいる始末だ。
周りはそんなことは知らず、大抵が「優等生」「神の子飼い」「いずれ上級に上がるエリート」のような評価が大半で、初めて寝所でのことが聞こえてきたときはデキウスが驚いた。
「ちょっと想像できん」
娼館では馴染みの香の香りが染み付いたシーツの上で、先ほどまで愉しんでいた戦女神とその兄神で怠惰なひと時を貪っていた。
「ああ、まだデキウスは知らないのか。ルベウスの仕事には閨房での仕事も含まれてるぜ」
「仕事じゃなくても、彼にとって意味がある相手なら来てくれるそうよ。私は振られっぱなしだけど。何に関しても淡白そうな彼がどう乱れるのか、神仕込みの閨房術も試してみたいじゃない?」
ルベウスを組み敷きそうなほど肉感的な戦女神が笑った。
後半部分は確かに思うことはあるな、とデキウスも頷く。
「乱れるどころか、徹頭徹尾サービス精神旺盛、めくるめく快感をくれるらしいが、コトが終わったら石柱相手のほうがマシだと思うらしいぞ」
「それは違う意味で興味を惹かれるな」
そんな会話をしたときは、まさか本当に自分がルベウスを欲しいと思う日が来るとは思っていなかった。
確かに性的なことは抜きで興味は大いに持っていたが、もし本当に寝たいと思うならそうすることに躊躇いなど覚えるはずもなかったのだ。
だが。
星の数ほどの相手と寝て、たまに飽き飽きとすることもあれど、身にしみついた快楽の愉しみから抜け出すことなどこの世が終わるまで無いだろうと思っていた自分が、わけのわからない沼に足を取られていた。
ルベウスの得意とする仕事ではなく、彼自身の意志で自分を求めて欲しいと思ったのだ。
おかげで自分で自分を常に欲求不満の状態に陥れてしまった。
誰を何人何度抱いても埋まらない渇き。
肉体を介在とする駆け引きならば息をするようにできたが、ルベウスが何を求めて何を喜ぶのか、何で気を惹かれるのかがさっぱり読めない状況で、ただ精神的な距離を詰めていくだけの作業は苛立つと同時に面白くもあった。
そして違う意味で新たな沼に足を突っ込んだ。
彼を寵愛する神に呼び出され、その目の前で伽をすることを命じられたのだ。さすがにルベウスに関わりすぎて不興を買ったかと思いもしたが、それならばデキウスにとって何の損失も発生しないどころかむしろ力を得ることになる役目を賜ることもなかっただろう。
唯一困惑したのは、抱きたいと思っている相手の前で抱かれることだったが。
おかげでその後、ルベウスとの間に妙な距離ができた。ルベウスにとって絶対的な存在で不可侵であり盲目的に敬愛する主人と、自分の意志で自分のテリトリー内に入れた男との房事はさすがに混乱を引き起こしたのだ。
彼が自分の感情を持て余しているのだと知ったときは、不謹慎にも嬉しくて笑いがこみ上げるのを隠せなかったのだが。
それは地上でお互いを堪能してからも、ルベウスの中を不定期に揺さぶるようで、それが何であるか指摘するのはデキウスの役目ではなかった。
今日もデキウスから見れば不機嫌そうに眉間を寄せ、肉体を纏って斎戒宮のエントランスの椅子に浅く腰掛け、背筋を伸ばして瞑目している。
フィディウスと同じ形の、地上では聖族が降臨するときに纏うと言われている法衣に身を包んでいたが、袖口や襟に銀糸の繊細な刺繍がほどこされていた。
最初の頃は気付かなかったが、それを纏っているときのルベウスは「仕事」として誰かの閨を訪れているらしい。
不機嫌そうな上にタイミングも悪いかと苦笑しながらも、そこで彼を避ける発想はない。
そっとルベウスの前に近づき、瞑想しているように静かな表情の(ただし眉間が寄っているが)ルベウスの顔をじっくりと観察していると
「これからか」
と唇が動いた。
「焼かれたばかりだが、足りなさそうに見えるか」
デキウスの言葉に、ルベウスの口端が上がり、薄蒼の双眸が開かれた。
「私はこれからだ」
「じゃあ何をしていたんだ、ここで」
デキウスは斎戒宮では眉を潜められるが、彼にとっては礼儀正しい距離をあけて隣に腰を下ろした。
「身中に澱のように溜まる穢れについて考えていた」
ルベウスがいつものように、淡いというよりも冷たいような温度の口調で答える。これで突き放されたような気持ちになる相手もいるだろう。
「分析するより焼かれたほうが早いだろう。考えたところで減りはしない」
「いかにも」
かすかに目で笑い、左右の指をあわせて尖塔のような形を作って考え込むように自分の唇につけた。
「それが明確なら避けられる気がしてな」
「避けたところで、三日目でここへくるのが五日目になるぐらいだろう? くだらん」
デキウスが心底そう言うと、ルベウスが横目で見て軽く眉を上げる。
「確かに。お前はシンプルでいい」
「お前が難しすぎるんだ」
デキウスの面倒くさそうな言葉に、ルベウスはうっすらと笑った。
「ではこういう例えではどうだ? お前の手元には一杯の水がある。とても貴重なものだ。そこに飢えて乾いた人が分けてくれないかとやってきた。半分分けてやったら、もっと欲しいと言う。どうする?」
「自分のものを見知らぬ奴に分け与える趣味は無い」
ルベウスは尖塔の指先で唇を軽く叩きながら「確かにな。だが神はお気に召さぬぞ」と言い、立ち上がった。デキウスの前に立ち、触れぬ程度の距離で見下ろす。
「欲しがるほうは強欲で、与えぬほうは吝嗇か?」
デキウスは薄蒼い瞳を見上げ、サラリと落ちて来たルベウスの髪の感触を頬で愉しんだ。
「どちらも穢れになる一つだな」
「だろう? 私は恐らく両方ある……」
ルベウスはデキウスではない遠くを見やり、独り言のように呟いて視線を戻した。周りに誰もいないことを確かめ、デキウスの口唇に人差し指で柔らかく触れた。近づいたことで、親しんだ花に似た香りが鼻腔を掠める。
デキウスの薄く開かれた場所から歯列を撫で、さらに口腔へ忍び入ると、舌を軽く押さえ、上顎を撫でる。深いキスをするときと同じように指先で中を確かめ、デキウスが自分を見上げて指の付け根まで舌を這わせるのを、目を細めて見ている。
水音が漏れ、ゆるゆると引き抜くと、デキウスに見せるようにそれを自分の口中へ差し入れ、舌を覗かせながら舐め上げる。そして濡れた指先を最後にデキウスの唇に塗りつけた。
「斎戒宮だぞ?」
デキウスが唇を舐めて笑う。
「どうせこれから焼かれるついでだ」
ルベウスはひらりと手をふると、デキウスから身を翻して斎戒宮の奥へと入っていく。
彼の過ぎた後に、仕事で移されたのであろう、ルベウスにはない香りが混じって残った。